前回の記事「ジュニアの保護者①」に引き続き、ジュニアテニス界における保護者問題について取り上げます。今回は実際にあったトラブル事例から、保護者が子供に与える影響について考察します。特に深刻なのが、子供の知らぬところで勃発する「裏バトル」の問題です。
【ケース2】裏バトル勃発 – 子供の知らぬところで…
親同士の喧嘩で子供を振り回してしまう保護者
これもジュニアテニス界でよく見かける、保護者が子供の邪魔をしてしまうケースです。
ジュニアテニスにおいて、以下のような場面で親同士の繋がりは必要不可欠です:
- ダブルスのペアリング
- 送迎の調整
- レッスン以外での練習
- 大会への参加調整
自然とスクールごと、クラスごとに仲の良いグループが結成されていきます。筆者は子供の親ではないので未経験ですが、そういった人間関係を大切にするのも一苦労でしょう。
しかし、その人間関係が原因で、思ってもいない方向に進んでしまうことがあるのです。
親同士のトラブルが引き起こす深刻な問題
移籍を余儀なくされるケース
トラブルの原因(実例)
- 子供同士の喧嘩が親に飛び火
- 子供の態度に他の親が口出し
- シンプルに気に食わないという感情的な対立
原因は様々ですが、親同士のトラブルは後を絶ちません。それが原因でスクールを移籍することも珍しくありません。
移籍後の悪循環
そんなことがあれば、すぐに噂が広まるのがテニス界の特徴です。移籍先のスクールでも他の保護者に警戒されて馴染めない状況に陥ることがあります。
最悪のシナリオ
- 親同士のトラブル発生
- スクール移籍を余儀なくされる
- 移籍先でも噂により警戒される
- 居場所を失う
- テニスからフェードアウト
嘘のような話ですが、実際にあった話です。そういう子に限って、子供はいい子だったり、才能がある選手であるから本当にやるせない気持ちになります。
大人 vs 子供という不平等な構図
大会での緊張した場面
大人同士の揉め事はイーブンな関係ですが、大人 vs 子供となったらどうでしょうか?当たり前に大人の方が圧倒的に強い立場にあります。
よくある問題のシナリオ
- ジュニアの大会で接戦になり、試合の緊張感が高まる
- 際どいボールも増え、ジャッジに関して揉める
- ここまではジュニアではよくある光景
- 基本的に選手同士で解決しなければならない状況
- そこに親が介入して外野から抗議
- アンパイア、大会本部に殴り込み
- 選手は泣き出してしまい試合中断
適切な介入と過度な介入の境界
子供では解決できない状況になった時に、親が守ってあげることは確かに必要です。しかし、親が勝手に揉めて、それに子供が振り回されるのは全く別の問題です。
これは前回の記事「ジュニアの保護者①」で取り上げた「親が頑張り過ぎちゃうパターン」と根本的に同じ構造の問題と言えるでしょう。
子供への深刻な影響
身近な大人からの影響
子供は身近にいる大人の影響を強く受けます。一番身近な親が揉めてばかりいる環境が、子供の成長にとってどれだけ悪影響かは容易に想像がつきます。
具体的な悪影響
- 人間関係への不信感
- 競技への集中力の低下
- ストレスによる心理的な負担
- テニスへの興味・関心の減退
- 社会性の発達への悪影響
指導者としての自己反省
これは親に限らず、指導者である筆者自身も同じことです。まだまだ子供に偉そうに言えるような人間ではありませんが、子供たちに見られているということを今後も忘れないようにしたいと思います。
古典からの教訓
千利休の言葉から学ぶ
「花の慶次」というマンガで千利休の次のようなセリフがあります:
「親とは、なんと書く?親とは木の上に立って見ると書く。木から下りてノコノコ子の喧嘩に行く親がどこにある!」
まさにその通りだと思います。親が子どもを信じて、暖かく見守らないと成長には繋がらないのです。
理想的な保護者の関わり方
「木の上から見守る」視点
適切な距離感の保ち方
- 子供の自主性を尊重する
- 必要な時にのみサポートに回る
- 他の保護者との健全な関係維持
- 感情的にならない冷静な判断
- 長期的な視点での子供の成長を重視
介入すべき場面と控えるべき場面
介入すべき場面
- 子供の安全が脅かされる時
- 明らかな不正やいじめがある時
- 子供が助けを求めている時
- 大人の責任として対処すべき問題
控えるべき場面
- 子供同士で解決できる問題
- 感情的になっている時
- 自分の価値観を押し付けたい時
- 他の保護者との競争心から
健全なコミュニティ作りのために
保護者間のコミュニケーション改善
建設的な関係構築のポイント
- 子供の成長を第一に考える共通理解
- 違いを認め合う寛容さ
- 冷静な話し合いの場の設定
- 指導者との適切な連携
- 長期的な視点での関係維持
スクールや指導者の役割
環境整備の重要性
- 保護者向けのガイドライン作成
- 定期的な保護者会の開催
- トラブル発生時の適切な対応システム
- 子供第一の環境作り
- 保護者教育の機会提供
指導者としての決意
子供たちのために
筆者自身、まだまだ未熟な人間ですが、子供たちに見られているという責任を常に意識していきたいと思います。保護者の皆さんと共に、子供たちが健全にテニスを楽しみ、成長できる環境を作っていくことが何より大切です。
継続的な自己改善
指導者として、そして一人の大人として:
- 常に冷静な判断を心がける
- 子供たちの模範となる行動を取る
- 保護者との建設的な関係を築く
- 自分自身の感情をコントロールする
- 長期的な子供の成長を最優先に考える
まとめ
ジュニアテニス界における保護者問題は、表面的には大人同士の問題に見えますが、その影響を最も受けるのは子供たちです。親同士のトラブルが原因で才能ある子供がテニスから離れてしまうことは、本人にとっても、テニス界全体にとっても大きな損失です。
千利休の言葉にあるように、親は「木の上に立って見る」視点を持つことが重要です。子供を信じ、適切な距離感を保ちながら暖かく見守ることで、子供たちは本来の力を発揮し、健全に成長することができるのです。
保護者、指導者、そして子供たち自身が、それぞれの役割を理解し、互いを尊重し合える環境を作ることが、ジュニアテニス界の健全な発展につながるでしょう。
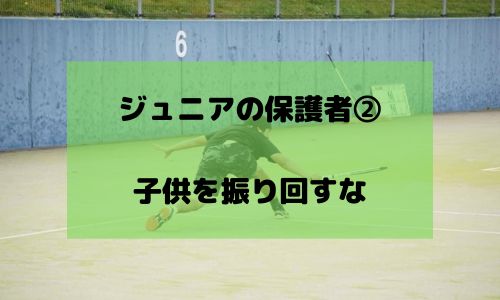
コメント