現代の子供たちを指導していると、一つの大きな課題に直面します。それは「全力を出すことを恥ずかしがる」という現象です。本記事では、この問題の背景と、仲間の力を活かした解決策について、実際の指導経験を基に詳しく解説します。
なぜ子供たちは全力を出すことを恥ずかしがるのか
「目立つことへの恐れ」という現代的課題
子供たちを見ていると、どうも「全力を出す」ことが苦手な子が多いと感じます。苦手というよりも、「恥ずかしい」という気持ちの方が強いのかもしれません。
なぜ、そう思うのでしょうか?一人だけ目立つことで、仲間から浮くかもしれないという「意識」が強く働くことがあります。これは現代の子供たちに特有の心理状態と言えるでしょう。
指導現場での具体的なエピソード
育成クラスでこういうシーンがありました。
球出し練習が終わり、ボール拾いの時間になると、ある選手はいつも駆け足で拾います。しかし他の選手は談笑しながらゆっくりと拾っている状況でした。
ポイント練習でポイントを取って「よっしゃ、カモン!」と喜ぶ選手に対して、他の選手から「うるさいなぁ」という反応が返ってきます。ポイントを取られて悔しさもあると思いますが、一生懸命な選手が逆に浮いているという現象が起きていました。
競争への複雑な感情
「競争」が人間関係の構築にマイナスである、という怖さもあるのかもしれません。勝負に真剣になることで友達関係が悪くなるのではないか、という不安を子供たちは感じているのです。
しかし、「勝負所」で自分の持てる力を全部出し切ることができる選手の方が、勝つ確率は間違いなく高くなります。これは紛れもない事実です。
真の「全力」とは何か
全力の出し方は人によって違います。しかし、全力を出している人に共通するのは、「気迫がある」ということです。
そんな雰囲気が、プレーにちゃんと現れます。そういうプレーを見ていると、大きな「可能性」を感じて嬉しくなります。「気迫」「全力」をちゃんと伝えられるように、恥ずかしくないことであることを、これからも指導していきます。
集団の仲間意識 – やる気を支える存在
真の「仲間」とは何か
前述の「全力」「やる気」を持ち続けるために大切なのは「仲間」です。ここで言う「仲間」とは、仲良しのグループということではありません。「やる気」を高めてくれる存在ということです。
真の仲間の例
- 切磋琢磨できるライバル
- 一生懸命頑張っている子
- 励ましてくれる仲間
- 刺激を与えてくれる存在
こうした「仲間」に巡り合うと、「やる気」はずっと続きやすくなります。
テニスの孤独性を超えて
テニスというスポーツは孤独なスポーツであると言われます。コート上では一人で戦わなければなりません。しかし、常にそういう仲間に刺激を受けることで、それを超えて強くなる意志、「やる気」が高まるのです。
仲間に巡り合う最良の方法
自分が、そういう存在になろうとすること。そう心掛けて頑張ることが、「仲間」に巡り合う一番良い方法です。
大きな「やる気」を感じると、強くなる可能性を強く感じます。育成クラスは個人で頑張るのではなく、頑張れる集団にしたいと常に思って選手と向き合っています。
仲間の力でパワーアップ – ダブルス練習の効果
シングルスとダブルスの心理的違い
普段はシングルス練習がメインですが、たまにネットプレーや状況判断の練習も兼ねてダブルス練習を行います。
ダブルス練習の良いところは、子供たちが楽しそうに練習することです。シングルスだと、思うようにプレーできなかったり、負けそうになると、自分を見失って雑なプレーをしたり、投げやりな態度になることも多くあります。
しかし、ダブルスだとそうしたことが大変少なくなります。
パートナーシップが生む好循環
パートナーに気を使って、ということもありますが、仲間と一緒にプレーをするということが良い効果を生みます。
ダブルスでの好循環
- パートナーと励まし合う
- ナイスショットを讃え合う
- コミュニケーションを取る
- 共に戦う一体感を味わう
これらのコミュニケーションには「心地良さ」があります。この心地良さが、選手たちの本来の力を引き出すのです。
シングルス能力向上への活用法
この効果をシングルスの能力を高めるために繋げていくことが重要です。そのためには、ただ楽しむのではなく、以下のような取り組みを心掛けます:
ダブルス練習での挑戦項目
- 様々なショットを使った攻撃
- 思い切ったポーチへの挑戦
- シングルスではあまりできないようなプレー
- 自分のプレーの幅を広げるような試み
これらの挑戦を通じて、選手たちは新たな可能性を発見していきます。
子供の成長に助けられる指導者の視点
進級判断の難しさ
ジュニアクラスの循環を図るとき、進級の判断にはいつも悩まされます。どのレベルの進級においても、様々な要素での判断が必要になります:
判断要素
- テニスのレベル
- 年齢
- 身長
- 伸びしろ
- 練習に対する取り組み方
クラブ運営の現実
しかし、クラブでは高校生になった子供たちは、部活動に制限され、また高校で多くの仲間と過ごす時間が楽しく感じてクラブを離れていく子は多くなります。
そうなると運営上の問題もあって、多くの子供たちが在籍してもらえるようにしていかなければならない、という裏事情もあります。結果的に、少し進級の判断が甘くなりすぎてしまったなと感じることもあります。
子供たちが見せる驚きの成長
しかし、多くの子供たちが想像を大きく越える技術の高さ、その成長に感動します。
まだネットを越えるぐらいの背丈なのに、ラケットをやっと振れると思えるぐらいの細い腕なのに、こちらが驚くようなプレーをする子供たち。そのプレーを見ていると、大きく可能性を感じ、感動します。
指導者としての愛情
今は多くの子供たちが在籍し、毎日楽しそうにテニスを頑張っています。その感動は、可能性を強く感じることや、プレーの素晴らしさに驚くことばかりではありません。
我が子を見守る親のような気持ち
これこそが、指導者として最も大切な感情かもしれません。技術的な成長だけでなく、人間的な成長を見守り、応援する気持ちです。
指導者が心掛けるべきこと
全力を出すことの価値を伝える
「全力を出すことは恥ずかしいことではない」ということを、言葉だけでなく実際の指導を通じて伝えていく必要があります。
具体的なアプローチ
- 全力でプレーする選手を積極的に評価する
- 仲間同士で認め合う文化を作る
- 競争と友情は両立することを示す
- 個性を尊重しながら向上心を育む
良い仲間関係の構築支援
指導者は単に技術を教えるだけでなく、選手同士の良い関係性を築くサポートも重要な役割です。
関係性構築のための工夫
- チーム戦形式の練習を取り入れる
- 互いを励まし合う場面を意識的に作る
- 違いを認め合う環境づくり
- 共通の目標に向かう一体感の醸成
長期的な視点での指導
目先の結果だけでなく、子供たちの長期的な成長を見据えた指導が重要です。テニスを通じて学ぶ人生の価値観は、競技を離れた後も大きな財産となります。
まとめ
現代の子供たちが全力を出すことを恥ずかしがる背景には、「目立つことへの恐れ」や「競争への複雑な感情」があります。しかし、真の仲間に支えられ、適切な環境が整えば、子供たちは本来持っている力を存分に発揮できるようになります。
指導者として大切なのは、技術指導だけでなく、子供たちが安心して全力を出せる環境を作ること、そして真の仲間関係を築けるようサポートすることです。ダブルス練習のような工夫を通じて、子供たちは自然と協力することの素晴らしさを学んでいきます。
そして何より、子供たちの無限の可能性を信じ、我が子を見守るような愛情を持って指導にあたることが、最も重要なことなのです。今後もレッスンをするコーチとして、この愛をもって子供たちと向き合っていきます。
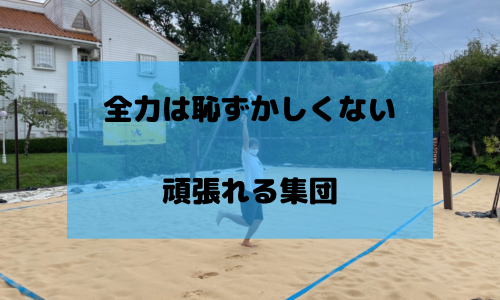
コメント