テニスの指導現場で「感覚を高めることが大事」という言葉がよく使われます。しかし、この「感覚」とは具体的に何を指すのでしょうか。本記事では、テニスにおける真の「感覚」の意味と、それを効果的に高める指導法について詳しく解説します。
テニスにおける「感覚」の真の意味
一般的な感覚の定義
感覚とは「目・耳・鼻などでとらえられた外部の刺激が脳の中枢に達して起こる意識の現象」のことで、五感と言われています。
テニスで重要な「感覚」
しかし、テニス指導で言う「感覚」はちょっと違います。それは以下のような能力を指します:
テニス特有の感覚
- 空間認知能力
- 時間感覚
- 先の展開を読む感覚
これらはスポーツ、特に球技などのパフォーマンスを高める上でとても大事な能力です。
具体的な感覚の働き
相手の打ったボールを適切に打ち返すために:
- ボールを打つタイミングを計る
- ボールとの距離を認知する
- 相手との距離を認知する
この能力が高ければ、もちろんパフォーマンスは高くなります。
ゴールデンエイジの重要性
感覚向上のための条件
この能力を高めることが大事ですが、そのために練習ではできるだけたくさんボールを打つことが大切です。そして、テニスをできるだけ早く始めることが何より大切なのです。
脳の発達と最適期
なぜなら、この能力を高めるには早い時期に適切な刺激が必要だからです。
神経系発達の科学的根拠
- 人の脳は10歳ぐらいでほぼ成人と同じぐらいに発達
- 10歳から12歳ぐらいは神経系の発達が著しい
- だからこの時期を「ゴールデンエイジ」と言う
その時に適切な刺激があるかどうかで、その後のパフォーマンスは大きく変わります。
スポーツの特異性
適切な刺激ということで、小さい頃に多くの経験をさせることが大事と言われますが、スポーツにはそれぞれ特異性があります。
他のスポーツや運動の刺激が、そのままテニスの微妙な技術の向上に役立つかどうかは、はっきりとはわかりません。
テニス特化の重要性
であるならば、小さい頃からテニスを始めた方が、テニスというスポーツそのものが適切な刺激になり得るということです。
そうした刺激を何度も何度も繰り返すうちに「感覚」は研ぎ澄まされ、五感を超える、理屈では説明できない**「第六感」も働くようになる**のです。
第六感の力
その「第六感」がパフォーマンスを大きく左右します。いいショットを打てるだけでは勝てません。大会を勝ち上がっている選手ほど、相手には見えていないものを感じ取れているのです。
たくさんボールを打つための工夫
ウォーミングアップの見直し
できるだけコートでボールを打つことを優先させたいので、ウォーミングアップはあまり重視していません。
トッププロであっても、アップをきちんとやらない選手は多くいます。アップより大切なものがあるのではないか、そう考えます。
時間効率の重視
限られた時間の中であるならば、たくさんボールを打つことが大切です。
ウォーミングアップを軽視するわけではありませんが、それを本格的にやるとなると、それなりに時間がかかります。実際のレッスンでは時間が少ないこともあって、どこのクラブでも十分にやれているとは言えません。
効率的な代替案
であるならば、それに多くの時間をかけず、練習への取り組みを早めに開始し、たくさんボールを打つほうが効率的です。
時間が十分にあるのであればいいですが、練習が始まってからみんなでストレッチなんていうウォーミングアップのカリキュラムは、無駄に時間を使います。
実践的な準備運動
ただし、いきなりの練習では身体的な準備が不足していることが多いので、練習前に軽いトレーニングをしたり、ミニゲームをしています。
効果的な準備運動の要素
- 練習前に身体の負荷を高める
- 心拍数を上げる
- 短時間で効率的に身体の準備をする
具体的な方法
実施している内容
- シャトルラン
- 動きの伴うボールを使ったミニゲーム
- 「イギリス」といわれる4人同時対戦のゲーム
これらの効果
- 一度に多くの子ども達がトレーニングできる
- テニスのフットワーク・技術の習得に役立つ
- 短時間で効率的に心拍数を上げることができる
大切なことは、限られた時間、短い時間で、より効率的に身体的な機能を向上させる方法を選択するということです。
お互いの感覚のズレを理解する
コーチングの変化
指導に関する考え方を整理してきましたが、選手の「感覚」を高めることを大切にする考えを持って指導していくと、「コーチング」に変化があります。
コーチングの効果を左右する要因
「コーチング」が活きるのは、その「コーチング」を受ける側の意識によって大きく変わることが分かっているからです。
よくある問題
選手がミスをするたびに、あれやこれや「コーチング」しますが、これは逆効果なことも多いのです。
熱心に教えているという印象を持たれるので、コーチとして優秀なのかなと見えますが、それが受け取る側に響いているのかというと、響いていないことも多くあります。
感覚のズレの原因
なぜなら、アドバイスされることが自分の感覚と合っていないことが多いからです。
よくある現象
- 「自分ではやっている」つもり
- しかし外から見るとまったく違うフォーム
- 「自分ではやっている」のにそれを指摘され続ける
- 「なんで?」となることも多い
効果的なコーチングの条件
なので、まずはじっくりと見る。その上で以下を確認します:
確認すべきポイント
- 今の問題点をどう捉えているのか
- それをちゃんと理解しているかどうか
- 混乱しているかどうか
よく判断し、その「感覚」をどうすれば改善できるか深く考えたうえで「コーチング」が必要です。
指摘以上の価値
それは単なる指摘ではないということです。アドバイスしたことが何かのきっかけになり、それが向上につながっていく、それが理想です。
しかし、そういう機会は思っているほど多くありません。
指導者の責任
筆者自身もジュニア時代に信頼していたコーチがいますが、その当時に何を教わったかと聞かれても、あまり記憶にありません。
だからこそ、アドバイスしたことがきっかけとなるように、自分自身がちゃんと研鑽していかなくてはならないと思います。
感覚を高める実践的指導法
段階的なアプローチ
初期段階(基礎感覚の育成)
- できるだけ多くのボール接触
- 様々な球種・スピードへの対応
- 基本的な空間認知能力の向上
中期段階(応用感覚の発達)
- ゲーム形式での実践
- 相手を意識した練習
- 時間感覚の精緻化
上級段階(第六感の醸成)
- 高度な状況判断練習
- プレッシャー下での感覚維持
- 直感的な判断力の向上
環境整備のポイント
物理的環境
- 十分なボール数の確保
- 多様な練習機会の提供
- 効率的な時間配分
心理的環境
- 失敗を恐れない雰囲気
- 感覚的な表現を受け入れる文化
- 個人差を認める指導姿勢
指導者の心構え
観察力の向上
- 選手の感覚的な表現を理解する
- 外見と内面のギャップを把握する
- 長期的な変化を見逃さない
コミュニケーション技術
- 感覚的な言葉を論理的に翻訳する
- 選手の表現に耳を傾ける
- 適切なタイミングでのアドバイス
まとめ
テニスにおける「感覚」の向上は、単なる技術練習では得られない貴重な能力です。空間認知能力、時間感覚、そして先読みの感覚は、ゴールデンエイジという限られた時期に、適切な刺激を与えることで効果的に育成できます。
重要なのは、できるだけ多くのボール接触機会を提供し、効率的な練習環境を整えることです。そして指導者は、選手の感覚的な表現を理解し、それぞれの感覚のズレを把握した上で、適切なタイミングでのコーチングを心がけることが求められます。
この「感覚」が高まれば、理屈では説明できない「第六感」も働くようになり、それがパフォーマンスを大きく左右します。選手が自ら感じ取れる能力を育てることこそが、真の競技力向上につながるのです。
指導者として、常に研鑽を積み、選手の感覚向上に寄与できるよう努めていきたいと思います。
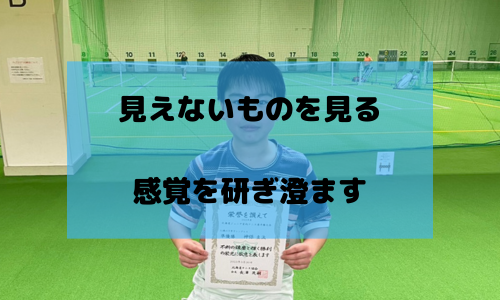
コメント