今年の北海道は雪解けが早く、あっという間に冬が過ぎた感覚です。そして北海道のジュニアにとって重要な外大会シーズンがスタートしました。GWには早速北海道ジュニアの各地域予選が開催され、秋から冬にかけて積み重ねた成果が問われる時期となります。
指導者としては、以前の記事「百聞は一見に如かず?」でも書いたように、試合観戦はエネルギーを使います。自分の選手の試合では感情も入り、結果に一喜一憂したい気持ちを押し殺しながら試合内容に目を向けて分析。加えてライバル選手の試合もチェックして、対戦時に対策が立てられるように情報収集を行います。
選手の緊張感とは違った緊張感があります。今回は、そんな様々な思いがぶつかる大会・試合がもたらす効果について詳しく解説します。
試合でしか味わえない経験
精神的成長の触媒
タイトルでも「試合は成長の大チャンス」と書きましたが、その通りです。
試合特有の心理的要素
- 絶対負けたくないという不安や恐怖を乗り越える勇気
- 絶対勝ちたいという欲からくる緊張感が引き出す高い集中力
これらの精神的なものが成長の要因になります。
「敗戦から学ぶ」能力の差
強くなる子とそうでない子の違いの一つに、「敗戦から学ぶ」ことができるかどうかがあります。ここで大きな違いが出てきます。
しかし、「敗戦から学ぶ」ことは簡単ではありません。理由は2つあります。
理由1:悔しさの度合い
1つは負けて悔しいという気持ちが強くなければ、そこから何も学ぼうという意志が生まれないことです。
子供の中には、負けてあっけらかんとする子もいれば、泣きじゃくる子もいます。その負けを受け入れているかどうか、悔しい思いがあふれているかどうかが重要です。そこは慎重な観察が必要です。
理由2:やる気の喪失
もう1つは、敗戦によってやる気が無くなることです。
やる気を失うきっかけはたくさんありますが、試合の負けでやる気が無くなってしまう子は、そこから学ぶことをやめてしまいます。
その気持ちを汲み取るのは簡単ではありません。子供の感情は大人よりもはっきりと出ますが、悔しい気持ちを表に出してはいけないという恥ずかしさから感情を隠すケースも多いのです。
観察の重要性
でも、よく観察して、その子の心の奥底、本当の思いを感じ取ることが大切です。何度も負けることで行動を変えた子が強くなることは間違いありません。それをうまく導くためには、ちゃんと観察すること、これが重要なのです。
試合と練習が結びついているか
理想と現実のギャップ
試合で勝つ、強い選手になる上で重要なことは「練習と同じプレーができる」ということです。
当たり前のことですが、そうでない子は多い、というかほとんどがそうです。
プレッシャーによる変化
負けたくないという思いが強く、プレッシャーが大きくなると以下のような変化が起こります:
技術面の変化
- 打つボールが変わる
- ミスを恐れるようになる
戦術面の変化
- 相手とのラリーから逃げる
- オーバーパワーになる
- コースを狙いすぎて無理な選択をしてしまう
成長する選手の特徴
でも、大きく成長していく選手は、そういう場面でも練習と同じプレーができます。
重要な理解
- もちろん、プレッシャーはある
- 負けるかもしれないという恐怖心もある
- 緊張しないわけではない
それでも練習でのプレーとの差が出ません。
そういう動きやスイングが完全に身体に染み付いているという感じです。だから、緊張はしてもちゃんと体が反応するということです。
技術レベルと心理的安定性
まだ技術レベルが低い子供たちは、ちょっとした動揺で心も体も変化します。普段通りではなくなって、どうしていいか分からなくなってしまいます。
改善のための練習意識
これを改善するには練習での意識が必要です。
問題点
- 多くの子供が練習のための練習をする
- 試合を想定できていない
- 同じ練習だが、試合の練習になっていない
- だから試合になると見失う
解決策 試合と練習を繋げていく。その意識が高ければ、きっと身体に染み付いていきます。それが当たり前のように試合でできるようになるのです。
試合は何が起こるかわからない
勝つことと負けにくいこと
試合で安定的に成績を残すには、「どうしたら勝てるのか」だけではなく、「どうすれば負けにくいのか」を考えることは大切です。
完璧主義の罠
人は誰でも「思うように勝ちたい」と思います。「完璧主義」になってしまうことは多いのです。
「完璧に自分の思い通り」を目指しますが、そんなことはめったにありません。世界のトップ選手でも、完璧に思い通りに試合に勝つことは人生でも数少ないと言われています。
テニスというスポーツの本質
テニスはミスが出る、ズレが生じるスポーツであることを忘れてはいけません。
もちろん完璧を目指すことは悪いことではありません。大切なのは、思い通りにならなかった時にどうするのかということです。
一般的な反応と強い選手の反応
一般的な反応
- 落胆し、やる気が下がる
- 戦う気力を失くす
強い選手・負けにくい選手の反応
- そういうことをちゃんと受け止める
- メンタル的にはそれなりに動揺するが
- 「今何をすれば勝てるのか」ということにちゃんとフォーカスできる
想定外への準備
想定外のことが起こる、思い通りいかないことは理解して、それに対しての準備や修正ができています。テニスというスポーツを甘くみていないのです。
これはやはり試合の経験の中でしか気づけない思考です。本気で勝つことにこだわれた選手が得られるメリットなのです。
指導者・保護者の適切な関わり方
気づきのチャンスを活かす
このように試合には気づきのチャンスが多く転がっています。このチャンスを逃さずに気づけた選手は、取り組み方に変化が出て、プレーに大きな変化を生み出します。
避けるべき声かけ
そんな成長・気づきのチャンスに、指導者・親の結果や内容に対するその時の感情に任せた声かけは無用です。
本物のアドバイス
選手が試合で感じ取ったことを引き出して、その経験が1番の収穫であることを気づかせてあげるような導きが本物のアドバイスです。
試合経験を最大化する実践的方法
試合前の準備
心理的準備
- 完璧を求めすぎない心構え
- 想定外の事態への対応策を考える
- 練習での動きを思い出す
技術的準備
- 練習と試合の連続性を意識する
- 基本動作の反復練習
- プレッシャー下での練習機会を作る
試合中の心構え
集中すべきポイント
- 今できることに焦点を当てる
- 練習通りのプレーを心がける
- 結果よりもプロセスを重視する
試合後の振り返り
効果的な振り返り方法
- 感情的になる前に客観視する
- 具体的な改善点を見つける
- 次回への具体的な行動計画を立てる
指導者・保護者の役割
- 選手の気づきを引き出す質問をする
- 感情に共感しつつ建設的な方向に導く
- 長期的な成長を信じて支える
まとめ
試合は単なる勝敗を決める場ではありません。選手が真の強さを身につける貴重な成長の機会なのです。
試合が提供する成長機会
- 精神的な強さの育成
- 敗戦からの学び
- 練習と実戦の橋渡し
- 想定外への対応力
- 自己分析能力の向上
重要なのは、試合の結果そのものよりも、その経験から何を学び、どう成長するかです。指導者と保護者は、選手が自ら気づき、学べるよう適切にサポートすることが求められます。
試合は確かに厳しい場面もありますが、それを乗り越えた時の成長は計り知れません。一つ一つの試合経験を大切にし、それを次の成長につなげていくことで、選手は技術的にも精神的にも真に強い競技者へと成長していくのです。
この貴重な成長のチャンスを最大限に活かし、選手一人ひとりの可能性を引き出していきましょう。
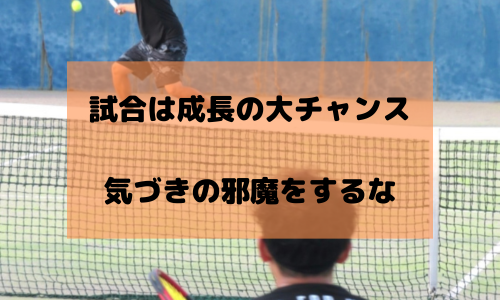
コメント