現代のスポーツ指導において、選手の「自立」を促すことの重要性がますます注目されています。本記事では、「何も言わないコーチング」の効果と、選手の自主性を育む指導法について、実践的な観点から詳しく解説します。
「何も言わないコーチング」が有効な理由
自立の前提条件
何も言わないコーチングが功を奏するのは、生徒の「自立」がある程度確立されているからです。
コーチに依存し、人に頼り過ぎる意識が強いと、「自分で考える力」が高まってきません。その結果、いざという時に弱い選手になってしまいます。
スポーツにおける「忍耐力」の真の意味
テニスに限らず、スポーツは「忍耐力」が勝敗のカギを握ることが多くあります。
ここで言う「忍耐力」とは、単に苦しい場面を耐え忍ぶということではありません。苦しい状況を打破するために何をすれば良いのかを考えながら、勇気を持って試行錯誤できることです。
忍耐力を培う方法
この「忍耐力」は、常に自分で考えることによって培われます。そのために「自主練」は効果的な練習方法と言えるでしょう。
コーチにとって勇気のいる「自主練」指導
指導者の葛藤
しかし、この「自主練」は、コーチにとってはちょっと勇気のいる練習です。
なぜなら、アドバイスをしないからです。端から見ると、何も仕事をしていないように映ってしまいます。
コーチにとって、こうした批判を受けるのは、ちょっと覚悟や勇気のいることです。(だから教えすぎになることも多々あります)
コーチングの本質的価値
でも、コーチングを深く考えると、こうした機会の創出が大事であると行き着きます。
もちろん、ただやらせておくわけではありません。コーチの仕事は、**「観察」**です。
観察すべきポイント
- 子どもたちが何をやりたがっているのか
- グループのコミュニケーションはどうか
- うまくいっていないことは何か
アドバイスをすることに追われて見るよりも、深く洞察することができます。良いアイディアが浮かぶことも多いのです。
考えたくなるような環境作り
興味を沸き立たせることの重要性
自分で考えさせる上でも、本人たちのテニスに対する興味を沸き立たせることは重要です。
筆者自身もそうですが、自分が関心のないことを考えろというのはなかなかの苦痛です。そして得た知識からの想像が膨らむことも少なくなります。
強制ではなく工夫を
なので、考えることを強制しすぎてはいけません。
重要な視点:考えることを求めるのではなく、考えたくなるようにする工夫が必要です。
具体的な工夫例
- プロの試合を観てイメージを作らせる
- 好きな選手を見つけて追いかけさせる
- テニスのどこに魅力を感じるかを探求させる
テニスのどこに魅力を感じるかは、生徒によってさまざまです。
意識だけで変わることもある – ミス軽減の実例
ミス軽減の難しさ
試合ではミスの多いほうが負けます。だから、「ミスをしない練習」をします。しかし、これがなかなか難しいのです。
練習の始めに「絶対にミスをしない気持ちでやりなさい!」と強く言いますが、実際の練習ではたくさんミスをしてしまいます。
基本ドリルでのミス
基本ドリルの練習など、打つボールは難しくありません。それでもミスをします。
劇的な変化
「今度はミスをしたらコートを走ってもらう!」と宣言すると、ミスは格段に減ります。
ミスをしたら「罰を与える」という方法が良いのか悪いのかわかりませんが、効果があるのは事実です。
変化の本質
しかし、結局のところ、ミスが減ったのは「絶対ミスをしたらダメなんだ!」と強く意識したからです。
この**「意識を高める」ことができればミスを減らすことができる**ということです。
理想の選手像
ミスをすれば負ける。だから、ミスをしないように強く「意識」する。ミスを「恐れる」と言っても良いでしょう。
それでもその「怖さ」に打ち勝ち、思い切ったショットを打ち込むことができる。そんな選手に成長してほしいと思います。
しかし、何度も言うように「意識を高めること」は難しいことなのです。
勝負にこだわる – 真の競技精神
意識が高まらない理由
なんで子供たちの意識は高まらないのでしょうか?そう考えたときに、「勝負に対する意識が低い」と感じます。
スポーツは「勝敗のつくもの」です。だとしたら、「何としてでも勝つ」そんな「意識の強さ」が必要です。でも、それが「薄い」と感じるのです。
勝つ喜びを知らない問題
理由はいくつか考えられますが、ひとつは**「勝つ喜びを知らない」**ということです。
「勝つ喜び」を感じるためには、「必死の戦い」が必要です。でも、多くの子供たちは、そういう場面にあっても「必死」がありません。
極限の気持ちの必要性
言葉は悪いですが、「ここで負けたら死んでしまう」ぐらいの気持ちがないということです。
そもそも競争が嫌なのかもしれません。でも、「勝敗のつくもの」である以上は、その「気持ちの強さ」が必要で、弱ければ負けてしまいます。
一般的な誤解
スポーツの解説なんかで、「あまり勝敗を意識しないほうがいいですね」なんて言いますが、強くなりたければ、「何としてでも勝つ」という意識は絶対的に必要なものです。
強さの始まり
そして、苦しい戦いをたくさん経験して、「もう負けたくない!」と強く思うようなところから強さは始まります。そういうものだと思います。
これからも子ども達に「勝負する心」の大切さを説いていこうと思います。
観る者の心を動かすプレー
応援したくなる選手
外から見ているほうも、「何としても勝ちたい」とプレーしている子を応援したくなります。
具体例:野球でいうと春のキャンプの練習試合よりも、日本シリーズの第7戦のほうが応援に熱が入るのと一緒です。
何かをかけて「負けないぞ」というプレーが心を打つものなのです。
目標:もっと勝ちにこだわらせよう!
自立した選手を育てる実践的方法
段階的なアプローチ
初期段階:依存からの脱却
- 簡単な判断から自分で決めさせる
- 失敗を恐れない環境作り
- 小さな成功体験の積み重ね
中期段階:思考力の育成
- 自主練の機会を意図的に作る
- 観察に徹する時間の確保
- 興味を引き出す工夫の実施
成熟段階:競争心の醸成
- 勝負の場面での意識向上
- 必死の戦いを経験させる
- 勝つ喜びを実感させる
指導者の心構え
観察力の向上
- 言葉で指示する代わりに深く観る
- 選手の内面の変化を見逃さない
- グループダイナミクスの理解
忍耐力の育成
- すぐに答えを教えたくなる衝動を抑える
- 選手の試行錯誤を見守る勇気
- 長期的な成長を信じる姿勢
環境整備の重要性
物理的環境
- 自由に練習できるスペースの確保
- 多様な練習道具の準備
- 安全で集中できる空間作り
心理的環境
- 失敗を受け入れる雰囲気
- 挑戦を奨励する文化
- 相互尊重の関係性
現代の課題と対応策
現代の子供たちの特徴
課題
- 指示待ちの傾向
- 競争への苦手意識
- 失敗への過度な恐怖
対応策
- 段階的な自立支援
- 競争の楽しさを伝える
- 失敗からの学びを重視
保護者・社会との連携
保護者への啓発
- 自立の重要性の共有
- 家庭での支援方法の提案
- 長期的視点の大切さの説明
まとめ
自立した選手を育てることは、現代のスポーツ指導における最重要課題の一つです。「何も言わないコーチング」は、表面的には指導者が何もしていないように見えますが、実際には深い観察と洞察に基づく高度な指導技術です。
選手が自分で考え、試行錯誤し、そして勝負にこだわる心を育てることで、真の強さを身につけることができます。意識の変革だけでも劇的な変化をもたらすことがあり、その意識を高めるための環境作りが指導者の重要な役割なのです。
競争を避けるのではなく、「何としても勝つ」という強い意志を持った選手を育てること。それこそが、観る者の心を動かし、選手自身も真の達成感を味わえる道なのです。勝負にこだわる心こそが、スポーツの醍醐味であり、人間としての成長にもつながる貴重な財産となるでしょう。
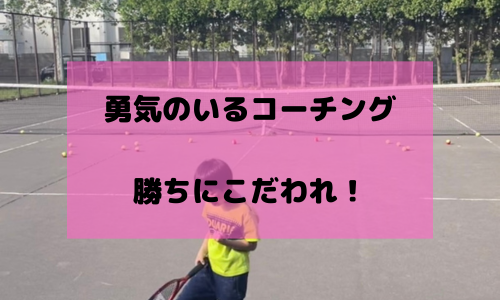
コメント