試合後の振り返りは、選手の成長にとって極めて重要な時間です。しかし、多くの選手が曖昧な感想しか述べられない現状があります。本記事では、この問題の背景と、効果的な振り返りを通じて選手の成長を促す方法について詳しく解説します。
なぜ試合後の感想が曖昧になるのか
よく聞かれる曖昧な感想
試合後に感想を聞くと、以下のような答えが返ってくることがあります:
- 「なんとなく」
- 「なんか微妙」
- 「よくわかんない」
なぜ、このような曖昧な言葉になってしまうのでしょうか?
曖昧になる背景要因
心理的な要因
- 報告することが面倒くさいという場合
- コーチとの信頼関係がなくて、話をすることに消極的という場合
- 負けて落ち込んでいる時に、いろいろと話すのはつらいという心理状態
これらの要因を理解した上で、適切なアプローチを取ることが重要です。
試合後の対話の真の目的
しかし、このような時にこそ、試合後のコメントを聞き、時間をかけて話し合いが必要になります。
重要な認識:この時間は、指導者が自分の意見を伝える場ではありません。
この場で技術的な問題点を数多く指摘しても、あまり効果はないのです。真の目的は以下の通りです:
試合後対話の目的
- 自分の弱さを認める
- それを克服するために自分の課題を整理する
- 強くなるためのヒントを探る
- 次の戦いに向けて自分の気持ちを奮い立たせる
しっかりと整理することで、それを繰り返すことで強い選手に必要なメンタリティーを獲得していきます。だからこそ、きちんと報告をしてほしいと思うのです。
経験の質と振り返りの関係
経験の質を測る指標
何かを経験した後に、何もコメントすることがなかったり、まともなコメントをすることができない状況は、その経験自体の質に繋がります。
もし、真剣に勝負を挑んだ試合であれば、勝ち負けに関わらず何かしら感じるものがあるはずです。それを素直にきちんと話すことが大切なのです。
一人で戦う選手へのアドバイス
しかし、一人で戦っている選手も多いでしょう。そういう選手は、ノートに自分の気持ちや分析した内容を記録するのも良い方法です。
ただし、書くには文章力などの適性もあります。試合後の報告に時間を取ることができるのなら、話すことがとても良いトレーニングになります。
対話から読み取れる情報
実際に話を聞いていると、その子供の思考や感性を感じ取ることができます。文章からそれを読み取ることは難しいものです。
よく話を聞き、それを記憶するのがコーチの役目だと考えます。大切なことは、何度も確認をすることです。そうすることで子供の感性が磨かれると信じています。
ゲーム感覚を磨く分析力
判断力と集中力の課題
育成クラスの子供たちは、技術はだんだんと向上していますが、ゲームで「判断力」や「集中力」に欠けることが多くあります。
実戦的な「ゲーム分析」
この課題を解決するために、「ゲーム分析」を実践しています。マッチ練習をする時に試合中にも声かけをして、分析をしながらゲームを進めます。
ゲーム分析の効果
- 単なる遊びに終わらない意識の醸成
- 集中力の持続
- 何かしらの「気づき」の獲得
- 駆け引きの向上
どれくらいの効果があったのかは明確に測定できませんが、駆け引きが出てきたように感じます。選手らしくなってきたということですね。
成長の「源」としての分析力
この分析力が成長の「源」になります。それをこれからもどう伸ばしていくのか、それは以下の要因にかかっています:
- 自分がどれくらい強くなりたいのか
- どれくらいテニスが好きになれるのか
指導者として、それをうまくサポートして伸ばしてあげたいと思っています。
「記録」ではなく「記憶」の重要性
目的を見失う危険性
本当に「自分のもの」にしているのか、というとそうではない場合があります。
普段の会話で、「コーチが話した内容はどういうこと?」と聞いてみると、答えはあいまいです。ちゃんと「記憶」していない、ということです。
よくある問題:学校の授業みたいなもので、話を聞くことが目的みたいになってしまうこと。
記憶できる選手の特徴
しかし、記憶できる子は、そこから大切なことだけをきちんと「記憶」します。そして、新しい知識を得る時には、記憶にあるものと関連づけながら、効率的に記憶して知識を深めます。
テニスでも同じです。ちゃんと「記憶」しているからこそ、様々な解決策を考えつきます。
記憶が不安を軽減する
不安な状況になっても、過去の経験が「記憶」されていれば、不安は小さくなります。
具体例:初めて入るお化け屋敷は不安や恐怖がいっぱいです。何度か経験すると、予測も準備もできるので、不安や恐怖は小さくなります。
それと同じようなものですが、前に入った時の記憶がなかったら、毎回同じような不安や恐怖が襲いますね。
「記憶」すべき内容
だから、子どもたちには、「記録」ではなく、「記憶」の重要性を説きます。
記憶すべき重要な内容
- 自分が大切だと感じたこと
- 「こうするんだ!」という強い決意
- 何をすれば強くなるのかという自分なりのアイディア
- 心に残ったアドバイス
どうしても忘れたくないことを、強く心に留めるために、より深く「記憶」することです。
指導者の役割と継続的サポート
応用力の課題
そうやって「強さ」を身につけていきますが、多くの子どもたちはそういう応用が苦手です。
これは一朝一夕には解決できない課題ですが、根気強く向き合って、強く心に「記憶」されるようにサポートしていこうと思います。
効果的な振り返りのための環境作り
信頼関係の構築
- 選手が安心して話せる雰囲気作り
- 批判ではなく、共に成長する姿勢
- 選手の感情を受け入れる包容力
継続的なサポート
- 定期的な振り返りの機会提供
- 記憶の定着を促す反復確認
- 個々の選手に合わせたアプローチ
長期的な視点での育成
振り返りの力は、テニスの技術向上だけでなく、人生全般において重要なスキルです。自分の経験を客観視し、そこから学びを得て次に活かす能力は、どのような分野でも価値のある能力となります。
具体的な振り返り促進方法
質問の工夫
曖昧な感想を具体的な振り返りに変えるための質問例:
技術面
- 「今日一番うまくいったショットは?」
- 「困った場面でどう対処した?」
戦術面
- 「相手のどこが強いと感じた?」
- 「自分の作戦は機能した?」
メンタル面
- 「緊張した場面はあった?その時どうした?」
- 「次の試合で試してみたいことは?」
段階的なアプローチ
- 感情の受け入れ:まず選手の気持ちを受け入れる
- 具体的な質問:段階的に具体的な内容を引き出す
- 整理と確認:学んだことを一緒に整理する
- 次への活用:次回に向けた具体的な行動を決める
まとめ
試合後の振り返りは、単なる感想を聞く時間ではありません。選手の成長を促す貴重な学習機会なのです。
曖昧な感想しか言えない背景には様々な要因がありますが、指導者が適切なアプローチを取ることで、選手は徐々に自分の経験を言語化し、そこから学びを得る力を身につけていきます。
「記録」ではなく「記憶」を重視し、分析力を育成することで、選手は単なる技術の向上だけでなく、自立した学習者として成長していきます。指導者は根気強くサポートし続けることで、選手の真の成長を促すことができるのです。
この継続的な振り返りの習慣こそが、強い選手に必要なメンタリティーを育成し、生涯にわたって価値のあるスキルとして選手を支えていくことでしょう。
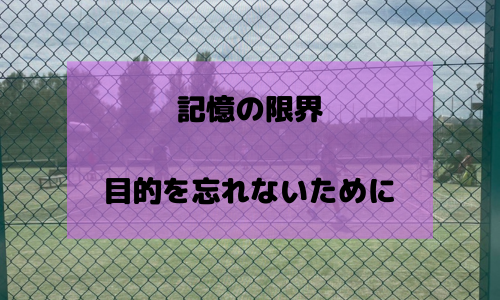
コメント